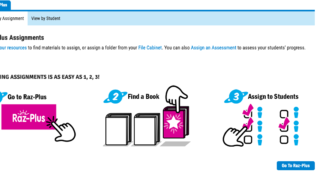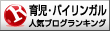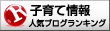「親子英語」「バイリンガル育児」では、インプットを得るために、「掛け流し」を行う必要があります。
掛け流し教材として我が家では、乳児は、Wee Sing シリーズ、七田の「さわこの1日」「ゆきおの1日」、DWE、児童英語教育所の「パルキッズ プリスクーラー」を流し、幼児は児童英語教育所の「パルキッズ キンダーキッズ」を流しました。
その後は、もっぱらラボ教育センターなどの絵本・物語CDを流しています。
教室に通っても、家で聴くCDが無いと英語を聴き取れるようにはならない!
教室に週に1回通うだけでは、到底英語を聞き取れるようにも、話せるようにもなりません。
と常々私はママ友に話してきました。
近年大手の英会話教室でも家で聴くための「お話CD」が教材として使用されるようになりました。
と嬉しく思っていましたが、それでもやっぱり
と思うところがあります。
英会話教室のお話CDが不十分だと思う理由
会話文を覚えて欲しいという大人の意図が埋め込まれているCD教材には、下心があり、聴いている子どもにとっては内容が薄っぺらく、子どもたちにとってはつまらないものなのです。
本物の絵本・物語の力
大人が与えたいものと、子どもたちが選びたいものは違う
例えば、「長くつ下のピッピ」を例にあげるとしましょう。
私は大人になってからこの本を読んだところ、主人公のピッピのことは、とても好きにはなれないし、物語を読み進めるのが苦痛になって途中で辞めてしまいました。
しかし、この物語は、子どもたちには大変人気があるのです。出版当時も、大人からは反対され、子どもたちからは高く評価さたのです。
サスケ(息子)が好きで毎週学校の図書館から借りてくる「1ねん1くみ シリーズ」も然りです。
大人は子どもに与えるものとして、「教訓になるもの」を選びがちですが、子どもたちはそうとは限らないのです。
むしろ、破天荒な主人公に憧れ、自分ができないような冒険へ行くような、夢や希望、理想を抱くのです。
余白を想像する余地のある本物の「絵本・物語」の凄さ
日常の一つの場面をCD教材にしたものを聴いていても、想像する余地はほとんどありません。そこが、本物との違いです。
本物の「絵本・物語」を聴いている場合は、「あれはどういうことかな?」「どうしてああなったのかな?」「その後はどうなったのだろう?」と、聴いている人の頭に絶えず色んな疑問を抱かせます。
例えば、我が家でよく流すお話の一つに「だるまちゃんとかみなりちゃん」というお話があります。
このお話を聴いていると、私は、
と色んな疑問が私の中に湧き上がってきます。
本物の「絵本・物語」と触れることで、「想像力」「考える力」「読解力」が育つのは、この「余白を想像する余地がある」からだと思います。
何度聴いても楽しむことができる、心に引っかかるフレーズと出会える、最高の「掛け流し教材」
好みもあるかと思いますが、「好きな絵本・物語は何度聴いても飽きない」けれども、一度読んだら満足してしまうような「語りかける力のない絵本・物語」にはもう二度と手を出しませんよね。
「会話を覚えることを目的として作られたCD」には、「何度も聞きたい!」と子どもたちを思わせる程の力はありません。大人と同じように「義務感」で聴くようになります。
あくまでも「掛け流し教材」なので、そこまで子どもたちの心に残る必要は無いかもしれません。
しかし、お子さんが小学校に上がり、日本語をフルにを使って勉強し、生活するようになっていくと、「子どもたちの心に引っかかるものであるかどうか」によって、どれだけ子どものたちの「心に残るかどうか」が違うように感じます。
そもそも、小学校へ上がると忙しくて「掛け流し」をする時間が減ったり、自我が強くなることで、「掛け流し」をすること自体が難しくなります。
嫌らしさのない本物の「絵本・物語」であるからこそ、小学生以上の子どもたちが、何度聴いても楽しむことができます。
そして、心に引っかかるフレーズと出会うことができます。
子どもたちの心に「訴える力」があり、子どものたちの「心へ届く力」があるのは、本物の「絵本・物語」だからこそだと思います。
まとめ 小学生以上の掛け流し教材として「絵本・物語」をすすめる理由
- 大人が与えたいものと、子どもたちが選びたいものは違う
- 余白を想像する余地があり、「想像力」「考える力」「読解力」が育つ
- 何度聴いても楽しむことができる
- 心に引っかかるフレーズと出会える
- 子どものたちの心へ届く力がある!